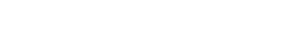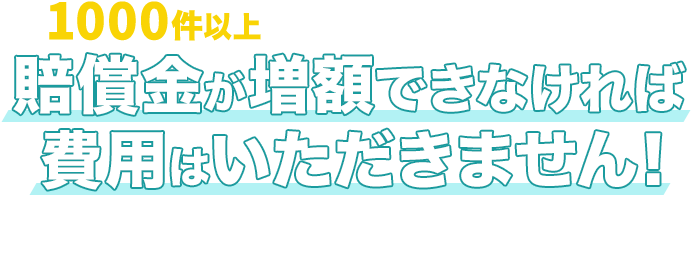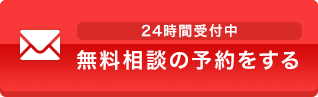損害賠償の「減額事由」とは?
損害賠償が減額される場合はあるのか?
被害者に生じた損害の全部を加害者側に賠償させることが、損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反する場合があり、総損害額中、加害者側が賠償すべき範囲を限定するための減額事由があります。
このように減額事由は、本来、法の理念に立脚するものですが、保険会社を背後に加害者側が損害自体の存否・範囲・金額を争うための、ツールともなっています。
任意保険で賠償金が支払われる場合、加害者や加害者の雇用主が被告となるといっても、背後には保険会社が控えており、通常、加害者側には、保険会社が指定した弁護士が代理人として選任されます。損害賠償額を減額しようとするのは、現象として当然のことです。
減額事由として次のようなものがあります。
- 過失相殺
- 素因減額(身体的素因(既往症)・心因的素因)
- 好意同乗
身体的素因(既往症)
最高裁判所昭和63年(オ)第1094号平成4年6月25日第一小法廷判決「被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である。けだし、このような場合においてもなお、被害者に生じた損害の全部を加害者に賠償させるのは、損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反するものといわなければならないからである。」
交通事故により傷害を被ったことに基づく損害賠償の額を定めるに当たり首が長いという被害者の身体的特徴をしんしゃくすることはできないとされた事例が有名です(最高裁判所平成5年(オ)第875号平成8年10月29日第三小法廷判決)。
最高裁は次のとおり説示しています。
「被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌することができることは、当裁判所の判例(最高裁昭和63年(オ)第1094号平成4年6月25日第一小法廷判決・民集46巻4号400頁)とするところである。しかしながら、被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり勘酌することはできないと解すべきである。ただし、人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものということはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されているものというべきだからである。
これを本件についてみるに、上告人の身体的特徴は首が長くこれに伴う多少の頸椎不安定症があるということであり、これが疾患に当たらないことはもちろん、このような身体的特徴を有する者が一般的に負傷しやすいものとして慎重な行動を要請されているといった事情は認められないから、前記特段の事情が存するということはできず、右身体的特徴と本件事故による加害行為とが競合して上告人の右傷害が発生し、又は右身体的特徴が被害者の損害の拡大に寄与していたとしても、これを損害賠償の額を定めるに当たり斟酌するのは相当でない。」
なお同じ日に言い渡された同じ小法廷が次の判決を言い渡しています(最高裁判所平成5年(オ)第1603号平成8年10月29日第三小法廷判決)。
「被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を斟酌することができることは、当裁判所の判例(最高裁昭和63年(オ)第1094号平成4年6月5日第一小法廷判決・民集46巻4号400頁)とするところである。そしてこのことは、加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、加害行為により被害者が被った衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等の事情によって左右されるものではないというべきである。
前記の事実関係によれば、被上告人の本件疾患は頸椎後縦靭帯骨化症であるが、本件において被上告人の罹患していた疾患が被上告人の治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していることが明白であるというのであるから、たとい本件交通事故前に右疾患に伴う症状が発現しておらず、右疾患が難病であり、右疾患に罹患するにつき被上告人の責めに帰すべき事由がなく、本件交通事故により被上告人が被った衝撃の程度が強く、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者が多いとしても、これらの事実により直ちに上告人らに損害の全部を賠償させるのが公平を失するときに当たらないとはいえず、損害の額を定めるに当たり右疾患を斟酌すべきものではないということはできない。」
心因的素因
心因的素因については、次の判示をした最高裁判所昭和59年(オ)第33号同63年4月21日第一小法廷判決が著名です。
「身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであつて、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができるものと解するのが相当である。」
好意同乗(無償同乗)
被害者が、加害者となる運転者との人的関係に基づきその好意で無償で同乗していたような場合を「好意同乗」とか「無償同乗」といいます。
加害者側としては、「タダで載せてやったのに何だ!!全部オレだけのせいにするのか?!」といって減額の主張をするのが通例です。ボランティアの法的責任が問題となる場面での議論に似ています。
過失相殺の場合に基準化されているのと異なり、類型的な基準が確立されていないのが現状です。
裁判例上も、好意同乗(無償同乗)であることのみを理由としては減額しておらず、好意同乗(無償同乗)の場合に減額を認める裁判例は少なからずあります。その場合危険な運転状態を容認又は危険な運転を助長、誘発したなどの場合には、加害者の過失の程度等を考慮のうえ、一定程度の減額を行うか、慰謝料額を減ずる扱いをしています。
そこで、このことを踏まえて、訴訟戦略を考えなければなりません。
ここでは、当法律事務所が担当した案件の中から、裁判所が、被告らの好意同乗減額の主張を排斥した事例を紹介します(札幌地方裁判所平成9年(ワ)第5035号同10年3月30日民事第2部判決)。
被告は、次のとおり主張しました。
「被告Aは、原告の勤務する会社の車を運転するよう強く求められ、やむなく二人で車の運転を交代しながら函館に向かい、函館では原告の実家に宿泊した者である。したがって、原告は好意同乗者であり、5割の過失相殺がされるべき事案である。」
これに対し、裁判所は、次のとおり判断しました。
「被告らは、原告はいわゆる好意同乗者であるから、5割の過失相殺がされるべきであると主張する。しかしながら、好意同乗者であることは、慰謝料等損害を算定する上での一要素として勘案されることはありうるものの、格別同乗者の帰責性が認められるなどの特段の事情もないのに、単に好意同乗者であることの一事をもって、過失相殺をすることは許されない。」
この判断は、当法律事務所が審理の中で提示した次のような主張を採用したものです。
「被告らは、本件はいわゆる好意乗車に該当し、5割相当の過失相殺が適用されるべきであると主張しているが、論理的に好意乗車が当然に過失相殺となるわけではなく、右主張は被告ら独自の見解というほかない。
判例では、同乗者自身において事故発生の危険が増大するような状況を現出させたり、あるいは事故発生の危険が極めて高いような客観的事情が存在することを知りながらあえて同乗した場合など、同乗者に事故の発生につき非難すべき事情が存する場合にはじめて減額を考慮することとし、単に好意同乗の事実だけでは減額は何ら法律上の根拠がなく許されないとされている。
そして本件では、原告には本件事故の発生につき非難すべき事情は全く認められないばかりか、そもそも本件は、原告後被告Aが、それぞれの所属会社の担当者の立場で共同して営業する必要から、交代で運転していたものであって、一方が運転している際に他方は好意同乗していると見る余地はおよそありえず、そもそも被告らの本件はいわゆる好意乗車に当たるという前提自体が全くの誤りであるといわなければならない。
被害者の自殺の場合
交通事故にあった被害者が自殺した場合、事故と自殺との間に相当因果関係が認められるときであっても、心因的要因を理由とする素因減額が行われるのが裁判例の傾向です。
前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
事務所全体で30社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。